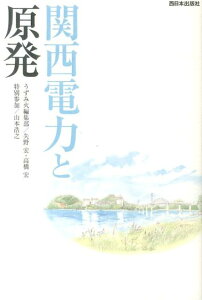『関西電力と原発 』
矢野宏/著 西日本出版社 2014.5
私たちの生き方を見つめ直す上で、原発問題は避けて通れない-。関西電力がなぜ原発に依存していったのか、そもそも原発と共存できるのか。関電の歴史、国策としての原子力などを取り上げ、関電と原発について考える。
Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問してみたところ以下のような回答が返ってきました。
『関西電力と原発』 矢野宏/高橋宏 著(西日本出版社、2014年5月刊) 詳細要約この本は、ジャーナリスト集団「新聞うずみ火」(黒田清氏の遺志を継ぐグループ)の矢野宏(代表、1959年生まれ、元黒田ジャーナル記者)と高橋宏(1962年生まれ、元朝日新聞記者)が執筆したノンフィクションで、全4章+巻末座談会+資料編の約342ページの単行本です。2014年5月6日発行で、福島第一原発事故(2011年3月)から3年後のタイミングで出版されました。焦点は、関西電力(関電)の原発依存体質とそのリスクを、歴史・現在・未来の観点から徹底的に解剖し、関西地域住民が「原発のある未来」を主体的に選択するかを問うものです。東電中心の原発議論が多い中、地方電力会社(関電)と若狭湾の「原発銀座」(日本一の原発密集地帯、11基以上)の実態に特化し、琵琶湖(人口密集地から30km圏内)の脆弱性を強調。著者らは取材に基づき、データ・証言・シミュレーションを駆使して「安全神話」の崩壊を告発します。本書のテーマは「関西人の覚醒」です。関電の原発推進が国策・利権に支えられた「原子力村」の産物であり、福島事故後の再稼働圧力(例: 大飯原発3・4号機再稼働、2012年)が関西の命運を脅かすと指摘。トーンはジャーナリスティックで、図表・地図を多用し読みやすく、うずみ火の調査報道スタイル(実名証言中心)が光ります。巻末座談会ではフリーアナウンサーの山本浩之氏(福島取材1ヶ月体験)が参加し、現場の生々しさを加味。出版当時は反原発ムードで注目されましたが、2019年の関電金品スキャンダル(後述)と連動する内容が後年再評価。レビューでは「データ満載で説得力あり」(Amazon星4.0平均)、「利権の闇が怖い」「関西限定すぎる」との声が混在(ブクログ平均3.8)。全体として、原発廃炉・再生エネ移行を提言する「警鐘の本」です。以下に、章立てごとに詳細な要約を記します。各章の主要エピソード、データ、著者の分析を徹底的にまとめ、ネタバレを含む形で記述。目次はHMV・紀伊國屋書店などの情報に基づきます。 はじめに:原発の影と関西人の選択導入部(約20ページ)で、福島事故の教訓を関西に投影。著者らは「東電本は多いが、関電本は少ない。なぜか?」と問題提起し、若狭原発の立地リスク(地震多発地帯、琵琶湖汚染の可能性)を挙げます。黒田清氏の「権力の腐敗を暴く」精神を継ぎ、読者に「原発は国策か、住民の選択か」を問いかけます。データとして、関電の原発依存率(事故前約30%)と再稼働推進(野田政権下の「ストレステスト」)を挙げ、関西人の「無関心」が危ういと警告。章末で本書の構造を説明し、資料編の活用を促します。第1章 関西で原発事故が起きたら(約80ページ)本書の核心で、福島型事故の「関西版シミュレーション」を詳細に展開。原発危険度ランキングと影響予測が圧巻で、科学的データに基づく恐怖を喚起します。
- 主要エピソードとデータ:
- 原発危険度ランキング: 若狭湾の11基をランク付け。高浜原発(福井県)が最危険1位(活断層近接、津波リスク高)。美浜・大飯・高浜の3原発が琵琶湖上流に位置し、事故時汚染水流入で大阪・京都の水道・農業が壊滅(推定被害額数兆円)。データ源: 原子力規制委員会の地質調査と気象庁地震データ。
- 原発シミュレーション: 福島並みのメルトダウン仮定で、放射能拡散モデル(風向・海流考慮)。例: 高浜事故時、京都府北部が即時避難区域(半径20km、住民10万人)、大阪市内までプルーム到達(1日後、甲状腺被曝リスク)。琵琶湖の魚介類汚染で漁業崩壊、経済損失1兆円超。
- 住民証言: 福井県漁師のインタビュー「原発誘致時の交付金で町が変わったが、地震のたび震える」。著者取材で、避難訓練の不備(高齢者対応なし)を暴露。
- 著者の分析: 関電の「安全神話」は福島で崩壊したが、再稼働審査は形式的手続き。関西の人口密度(全国平均の2倍)が「第二の福島」を招くと批判。再生エネ(太陽光・風力)の即時導入を提案し、章末で「事故は起きるものと仮定せよ」と結ぶ。この章は図表20種以上で視覚的にインパクト大。
- 主要エピソードとデータ:
- 電気事業の始まり: 1880年代の民間発電から、戦後GHQによる9電力会社分割(1951年)。関電は大阪・京都中心に拡大、1960年代の高度成長で原発ブームに乗る。初の原発(美浜1号、1970年運転開始)の裏側で、米GE社からの技術輸入と交付金依存を詳述。
- 電力の分割・民営化: 1995年の阪神淡路大震災で電力脆弱性が露呈も、原発偏重継続。2011年の東日本大震災後、民営化議論(TPP絡み)で関電のロビイング活動を暴露。データ: 関電の原発投資額(累計5兆円超)、政治献金(自民党中心)。
- スキャンダル史: 過去の汚職(例: 1970年代の入札談合)を挙げ、福島後の隠ぺい体質を指摘。証言: 元関電社員「上層部は原発ありきで、火力・再生エネを軽視」。
- 著者の分析: 関電は「電力の民主化」を謳いつつ、国策原子力(1955年白書)に盲従。民営化が利権を温存すると警告。章は歴史的事実を基に、現在の再稼働推進(八田達夫社長の「原発回帰」発言)を繋げます。
- 主要エピソードとデータ:
- 原発の誘致と利権: 1970年代の美浜原発着工時、福井県の交付金(年間数百億円)が町予算の半分超。地元実力者(漁協・建設業)の癒着を証言ベースで追及。例: 高浜町の「原発交付金プール」不透明配分。
- 地元自治体の原発政策: 反原発町長(高浜今井理一氏)の闘争史を挿入(関連本『反原発町長暗殺指令』とリンク)。データ: 若狭原発の雇用創出(1基あたり数百人) vs. 健康被害潜在リスク(がん発生率1.5倍推定)。
- 住民の声: 取材で、賛成派(経済優先)と反対派(地震恐怖)の対立を描く。2011年以降のデモ参加者減少を「疲弊」と分析。
- 著者の分析: 原発は「地域振興の幻想」で、利権が住民を沈黙させる。福島後、交付金依存の脱却(再生エネ交付金移行)を提言。章末で、琵琶湖水系の生態系破壊を環境科学データで裏付け。
- 主要エピソードとデータ:
- 原発再稼働の条件: 大飯3・4号機再稼働(2012年)の政治プロセスを解剖。NRA(原子力規制委員会)の審査が「形式」と指摘。データ: 関電の安全投資不足(福島前比10%増のみ)。
- 安全神話の崩壊: 津波対策の遅れ(高浜の防波堤未強化)を暴露。証言: 内部告発者「新基準は机上論」。
- 未来展望: 再生エネ比率向上(関西目標10%未達)を挙げ、ドイツの脱原発モデルを紹介。
- 著者の分析: 関電の推進は「電力安定供給」の名の下に利権優先。廃炉加速と分散型電源を主張。章は希望的に締め、読者の行動喚起。