『フクシマ発再生可能エネルギーの最前線』 Fh選書
久慈力/著 批評社 2016.3
東日本大震災後、世界で有数の再生可能エネルギー先進地となった福島県。県、市町村、企業、法人団体、民間団体、県民が一致結束し、海外とも連携しながら進められている福島県の再エネ開発の現況を紹介する。
Xの人工知能Grokにこの本について徹底的に詳細な要約を書いてくださいと質問したところ以下のような回答が返ってきました。
『フクシマ発再生可能エネルギーの最前線』 詳細な要約書籍概要本書は、2011年の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故を契機に、福島県が再生可能エネルギー(再エネ)の推進で復興の道を歩む姿を、著者・久慈力が現地取材に基づいて詳細に描いたノンフィクションである。批評社から2016年3月に刊行された『Fh選書』(Fukushima-hatsu選書)の一冊で、全222ページ。福島を「再生可能エネルギー先駆けの地」として位置づけ、脱原発の観点から自然保護と持続可能なエネルギー社会の構築を提唱する。政策、団体活動、具体的な事業事例、技術開発、リサイクルまでを多角的に解説し、福島の再エネ運動が日本全体や世界への情報発信として機能する可能性を強調。著者は環境問題に長年取り組むノンフィクション作家で、反原発運動の経験を活かし、現場の声やデータを交えて読者に訴えかける。全体として、被害からの回復力と未来志向の希望を軸に、環境・経済・社会の統合的な視点を提供する。著者背景久慈力(くじ・つとむ、1949年生まれ)は、岩手県八幡平市出身のジャーナリスト・ノンフィクション作家。1970年の「公害元年」を機に環境問題に目覚め、自然保護活動、姫神自然塾の運営、脱原発運動に深く関わる。盛岡在住時には、滝沢村の医療用放射性廃棄物処理場誘致反対や三陸原発計画反対運動を主導。ユーラシア大陸規模の古代史研究でも知られ、環境と文化の交差点で執筆を続ける。本書では、福島の被災地を繰り返し訪れ、地元住民、行政、企業関係者へのインタビューを基に、客観性と情熱を両立させた筆致で語る。章ごとの詳細要約本書は序章・10章・終章からなり、福島の被害実態から始まり、再エネ政策の深化、現場事例、未来課題までを時系列・テーマ別に展開。以下に、各章の主な内容を徹底的に要約する。序章 東日本大震災による福島県の苛酷な被害状況東日本大震災(2011年3月11日)の福島県への影響を、地震・津波・原発事故の三重苦として克明に描写。死者・行方不明者数、避難者数、放射能汚染の広がり、経済損失(農業・漁業の壊滅)をデータと現地写真で示す。福島の伝統的なエネルギー依存(原発中心)を振り返り、事故がもたらした「エネルギー転換の必然性」を指摘。著者は、被害の苛酷さを「再生の原動力」として位置づけ、再エネ導入が「脱原発の象徴」となる福島の役割を予感させる。この章は全書のパースペクティブを設定し、読者に感情移入を促す導入部。第1章 福島県は「再生可能エネルギー先駆けの地」となる福島が再エネの「聖地」として再生する基盤を論じる。震災直後の混乱から、2011年7月の「福島再生可能エネルギー構想」策定までを追う。県知事・佐藤栄佐久のイニシアチブと、太陽光・風力・バイオマス・地熱などの多様な再エネ資源のポテンシャルを、地形・気候データで分析。目標として、2020年までに再エネ比率を50%以上(全国平均の数倍)とする県計画を紹介。課題として、送電網の脆弱性や投資不足を挙げつつ、EU諸国(ドイツのEnergiewende)の事例を対比。福島を「世界のモデルケース」として位置づけ、復興が「グリーン・ニューディール」となる可能性を強調。第2章 福島県における再生可能エネルギー関連団体の結成再エネ推進の草の根運動を焦点に、NPO・市民団体・企業連合の形成過程を描く。震災後、福島再生可能エネルギー事業化推進協議会(FREA)の設立(2012年)を中心に、約100団体のネットワークを詳述。著者はインタビューを通じて、被災者主導の「ボトムアップ」アプローチを称賛。例として、会津若松の「会津電力」プロジェクト(地元出資の太陽光発電)を挙げ、資金調達の苦労と成功事例を具体化。団体の役割として、政策提言、技術共有、住民啓発を挙げ、原発事故がもたらした「連帯の力」を象徴的に語る。第3章 福島県の再生可能エネルギー政策の「核」となる事業県の主力事業を深掘り。福島イノベーション・コースト構想(FIC)の概要と、再エネ関連投資(総額数兆円規模)を説明。太陽光発電所の大量導入(メガソーラー)、小水力発電の河川活用、木質バイオマスの森林資源利用を事例に挙げる。経済効果として、雇用創出(数千人規模)と地元産業振興をデータで示す。課題はFIT(固定価格買取制度)の活用と、原発廃炉費用との競合。著者は、これら事業が「福島ブランド」の回復に寄与すると分析。第4章 内堀雅雄福島県新知事による再生可能エネルギー政策2014年就任の内堀知事の政策シフトを検証。佐藤前知事の基盤を引き継ぎ、「福島イノベーション構想」を加速。知事の公約として、再エネ輸出(アジア向け技術移転)と国際連携(IAEAとの協力)を強調。著者は知事インタビューを基に、行政の「トップダウン」改革を評価しつつ、官僚主義の残滓を批判。政策の成果として、2015年の再エネ設備容量増加(全国1位)を挙げ、福島を「エネルギー・イノベーションのハブ」へ変革するビジョンを描く。第5章 福島県から情報発信を世界に向けて行う再生可能エネルギー産業フェアの開催「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア」(通称:再エネフェア)の歴史と意義を詳述。第1回(2012年)から第3回までの変遷を追い、来場者数(数万人)、出展企業(200社以上)、海外パビリオン(ドイツ・デンマーク)の様子を生き生きと報告。フェアの役割として、技術展示、ビジネスマッチング、PRを挙げ、福島のイメージ転換(「汚染」から「革新」へ)を成功要因とする。著者は、フェアが「福島発」のグローバル発信ツールとして機能した点を高く評価。第6章 逆風にもめげず成功した第4回「ふくしま復興・再生可能エネルギー産業フェア2015」第4回フェア(2015年)の詳細レポート。台風被害や放射能懸念という逆風下での準備過程を、裏側から描写。来場者記録更新(4万人超)、新技術デモ(ドローン太陽光点検)、若手起業家ブースの活躍を具体例に挙げる。経済効果(取引額数百億円)と、被災企業再生のストーリーを感動的に語る。著者は、この成功が「福島のレジリエンス(回復力)」の証明だと結論づけ、再エネが「希望のシンボル」となる。第7章 最先端を走る福島県内、郡山市内の再エネメーカー、再エネ団体の状況郡山市を中心とした地元企業の現場取材。太陽光パネルメーカー(例:シャープ子会社)、風力タービン開発企業、バイオマス発電所の事例を、生産規模・技術スペック・雇用状況で分析。団体の連帯として、福島再エネ産業クラスターの形成を指摘。課題は人材不足とサプライチェーンの脆弱性。著者は、被災地企業の「イノベーション力」を称え、日本全体の再エネ産業モデルとして提案。第8章 東北の被災地企業は産総研支援プログラムによって新たな技術の創出を目指す産業技術総合研究所(産総研)の支援プログラムを焦点に、東北被災企業の技術革新を描く。補助金活用のR&D事例(例:耐震型太陽光モジュール、地熱探査AI)を詳述。産総研の役割として、共同研究・特許取得支援を挙げ、成果として10件以上の新技術商用化を報告。著者は、このプログラムが「震災の教訓を活かした持続的イノベーション」の好例だと評価。第9章 再生可能エネルギーのハイブリッド技術の数々再エネの多様性を活かしたハイブリッドシステムを専門的に解説。太陽光+蓄電池、風力+水素発電、バイオマス+地熱の組み合わせ事例を、効率データ(発電率向上20-30%)で示す。福島の実証プロジェクト(会津のマイクログリッド)を中心に、安定供給の課題解決を議論。著者は、ハイブリッドが「原発依存脱却の鍵」であり、福島の多様な地形が最適地だと主張。第10章 再生可能エネルギーのリサイクルに取り組む国内発のパイオニア企業、環境保全サービス再エネの「サーキュラーエコノミー」側面を強調。使用済み太陽光パネル・風車ブレードのリサイクル企業(例:環境保全サービス社)の取り組みを、処理技術(化学分解・再利用率80%)で紹介。廃棄物問題の予測(2030年までに数万トン)と、県の補助制度を分析。著者は、リサイクルが「環境負荷ゼロ」の再エネ社会を実現し、福島がパイオニアとして貢献すると展望。終章 使用済再生可能エネルギー設備のリユース・リサイクル適正処分全書を総括し、再エネ設備のライフサイクル管理を提言。リユース(中古パネルの輸出)、適正処分法、国際基準(EUのWEEE指令)の導入を呼びかけ。福島の経験が全国・グローバルスタンダードになると予測。著者は、読者に「福島から学ぶ脱原発の道」を促し、希望に満ちた締めくくりとする。全体の評価と意義本書は、データ・インタビュー・写真を豊富に用い、政策論と現場物語のバランスが優れている。福島の再エネ推進が、単なる復興策ではなく、日本エネルギー政策の転換点であることを示唆。批評的な視点として、行政の遅れや投資格差を指摘しつつ、ポジティブな未来像を描く。環境意識の高い読者や政策関係者に推奨され、震災10年後の文脈でも価値ある一冊。レビューは少ないが、専門家から「福島の隠れたイノベーションを可視化した好著」との声がある。
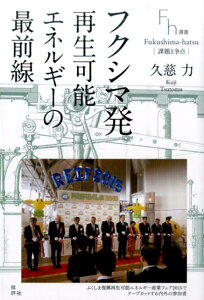 フクシマ発再生可能エネルギーの最前線 |